



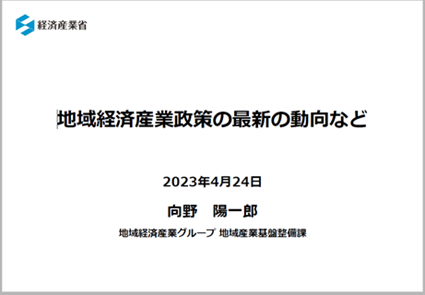
概要
国際秩序の急激な変容、個人意識の多様化、SDGsや地球環境問題などの社会視点・地球視点の必要性、さらにはICTによる情報や技術レベルのリアルタイムでの普遍化、等々、世界の動きへの幅広い視座と、それを積極的に活用・推進していくことが求められている。この状況に応える第一歩としての “気づき”醸成を目指すのが本科目である。日本そして世界で “ビジネス創造推進” に携わる政府や専門家とのセッションを中心に置き、学生と講師、外部専門家の間での積極的な “対話” を持っていく事で、この新たなキーワード「ビジネス共創」を探り、これからの社会創造への気づきやビジネス共創の可能性理解の拡大を目的とする。
科目情報
| 科目名 | 学期 | 科目番号 |
|---|---|---|
| 創造的ものづくりプロジェクトIK ‐世界のビジネス共創を探る‐ | 学部3年生S1S2 | FEN-CO3g11P2 |
| 創造的ものづくりプロジェクトIIIK ‐世界のビジネス共創を探る‐ | 学部4年生S1S2 | FEN-CO4g71P2 |
| 創造性工学プロジェクトIK ‐世界のビジネス共創を探る‐ | 大学院修士・博士S1S2 | 3799-511 |
※最新の開講状況はシラバス・便覧をご確認ください。
指導教員
高鍋 和広・佐藤 千惠
活動内容
| 回 | 日 | 内容 <>内はゲストスピーカー |
| 1 | 4/10 | オリエンテーション、「国際ビジネス共創とは」講義 |
| 2 | 4/17 | 全般準備、対話①の準備ワーク |
| 3 | 4/24 | 対話① <経産省関東経産局 総務企画部長 向野陽一郎氏> |
| 4 | 5/1 | 対話①レビュー、対話②の準備ワーク |
| 5 | 5/8 | 対話② <Finland Enter Espooシニアアドバイザー清水眞弓氏> |
| 6 | 5/15 | 対話②レビュー、対話③の準備ワーク |
| 7 | 5/22 | 対話③ <Uzbekistan UJICY 専門家 柳田行範 氏> |
| 8 | 6/5 | 対話③レビュー、対話④の準備ワーク |
| 9 | 6/12 | 対話④ <共創コンサルタントICMG Singapore辻悠佑氏> |
| 10 | 6/19 | 対話④レビュー、対話⑤の準備ワーク |
| 11 | 6/26 | 対話⑤ <横浜市経済局新産業創造課課長 大橋直之氏、 横浜みなとみらい21事務局長 古木淳氏> |
| 12 | 7/3 | 対話⑤レビュー、最終発表準備 |
| 13 | 7/10 | 最終発表 |
全5回の対話内容
第一回:経産省関東経産局 向野陽一郎氏
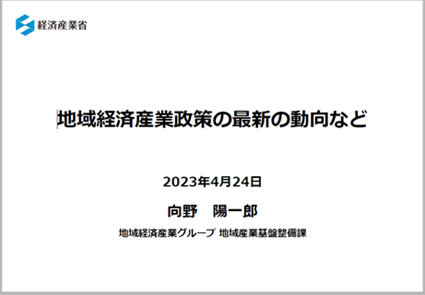

講演概要
● 講演は、多様な施策やプロジェクトの事例を挙げつつ、以下の四点で構成
①経済産業省・関東経済産業局の組織と役割
② “共創”を前提とした地域施策の展開~自前主義からの脱却~
③ 政策立案における共創の本質
●まとめ
1) 政策立案は(国内外問わず)“共創”が基本であり、計画策定に当たっては、組織内でも徹底した対話を通じた共創が発生した上で、関係機関との調整が発生。調整に当たっては、先方の利益や立場を十分考慮する必要あり。
2)>関係機関との調整に当たっては、地域ニーズを踏まえている事、着地点の明確化とそれに合わせた調整、さらには調整後に実際に「積極的な汗かきができるか」といった点を重視
第二回:Finland Enter Espoo社シニアアドバイザー 清水眞弓氏


講演概要
● フィンランドの先端イノベーション都市であるEspoo市の投資誘致・共創推進機関であるEnter Espooの活動を通じた“共創“の実態についてオンラインで講演
●まとめ
1)フィンランド、及びエスポー市について
2) エスポーのイノベションコミュニティについて: 分野横断的な画期的創造力の素地、目的意識の共有、物理的・心理的距離の近さと信頼感、住民のウェルビーイング
第三回:Uzbekistan UJICY Director Nargiza Amirova 氏、専門家 柳田行範 氏


講演概要
● ウズベキスタンにおいて日本と連携した大学研究推進機関として活動するUJICYから、Director(所長)のAmirova氏、及び専門家の柳田氏によるオンラインでの講演
●まとめ
① ウズベキスタンとUJICYの概要
② 様々な共創活動(若い世代、女性、産業)
③ 異文化共存環境における共創へのチャレンジと、UJICYの役割
第四回:共創コンサルタントICMG Singapore辻悠佑氏(在シンガポール)


講演概要
● シンガポールにて日本企業のアジア諸国事業展開支援を行っているコンサルタントの立場から、「イノベーションネーション・シンガポールの最前線を理解し、共創型イノベーションの学びを深めること」を主目的として、下記内容をオンラインで講演
●まとめ
① シンガポールのイノベーションエコシステムの最前線
② シンガポールにおける⽇本企業のイノベーション活動の実態
③ これからの時代の⽇本企業の共創型イノベーションのポイント
第五回:横浜市経済局新産業創造課課長 大橋直之氏、横浜みなとみらい21事務局長
古木淳氏
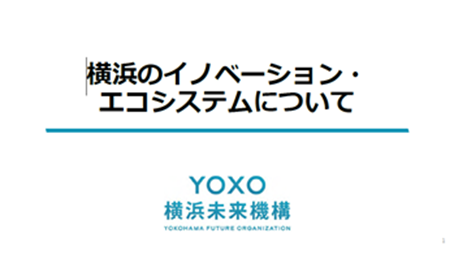

講演概要
● 横浜市をフィールドとして企業、大学、行政が垣根を越えてイノベーション創成を目指す市の活動の要となる部局の大橋氏が基本として講演し、さらにその中核エリアのみなとみらい21地区の企業コンソーシアム(一社)横浜みなとみらい21の事務長として地元企業の動きを見てきている古木氏から、現場の企業の動きなども伺う形で実施
学生の声
第一回
・摺り合わせの重要性を実感
・決まった手順を踏む、との従来のお役所対応が変わっていけるのか?!
・ 共創には「数字」と「感情」のバランスが重要だが、数字には強い省庁であっても、感情の面を今後どのように扱えば良いのか、が気になる
・ 企業と異なり、最終的決定を誰が行うのかが明確でないように思われる省庁の場合、庁内多部局間での共創を進める上での問題はないのか?
・ 省庁として共創を扱う上では、団体や企業との接点だけで無く、個々人や小さなコミュニティの思いも受け取らなくてはいけないため、その部分を自分個人としてもどのように汲み取りながら関与すべきか、といった点を意識できた
・ 省庁は「背中を押してくれる役割」を持っている事を理解出来た 等々
第二回
「社会性」の背景を理解し、共創の形の違いを理解すべきだ!との点を気づかされた
・ (ビジネスを語る時には必須と思っていた)「競争」との言葉が出てこないのが印象的
・ 政府の透明性につながる情報提供の仕方、の重要性を意識した
・ 共創=異文化交流、と思っていたが、違うとわかった
・ 共創を実現するには、小規模で経済力と教育レベルが高い事が必要条件では?
・ (共創が常に正解ではなく)テーマによっては政府のトップダウンもあり。また対立国同士の場合、共創(だけを目指す)のは良い選択肢ではないのでは? 等々
第三回
・ ウズベキスタンの特性の数々を初めて知った:女性の多さ、ソ連の影響、イスラム、等
・ 第一次産業の新しい意味?が同国から見られそうな気がする
・ 持たない事を利点にできないか? 但し、持たない事が搾取につながってはまずいが。
・ 搾取につながらないために、ゲーム理論での限定された合理性を考えるべきでは?
・ (共創と言う前に)同国人が他国に流出するリスクは? 雇用条件や愛国心で対応か?
・ UJICYによるナッジ活動が印象的 等々
第四回
・今までの中での共通点も見えてきた: 例えば「共創する同士は対等」「いずれにしても政治的な意識は関与する」
・ 共創は掛け算。そしてゴールが一致していないと成し得ない。
・ ストーリ-性のない日本の問題を実感。本来持っているものが見えていないのでは?
・ 熱意で動く時代だという点が分かったが、その熱意の多寡の違いはどこから?
・ 日本は三方良しで地味・真面目・ルール遵守だが、特に国際環境では、これを柔らかくしつつ、事なかれ主義に走らない考え方が必要では? 等々
第五回
・ 首都圏内だが知らなかった横浜市の活動や魅力などを新たに認識した、との声多数
・ 横浜未来機構の様な活動と自治体の関係、官公庁視点(規制緩和と補助金)以外の共創推進のあり方の深耕の必要性、地域関係者の熱意の取り込み方、横浜市ならではのストーリ-とは?、共創活動と共創に向けた交流推進の関係性、等々


学生発表スライド
